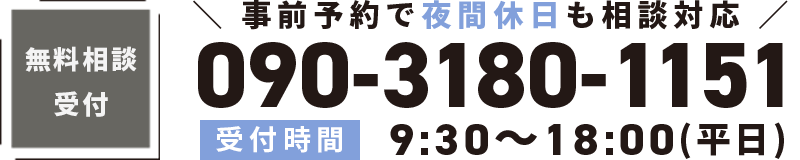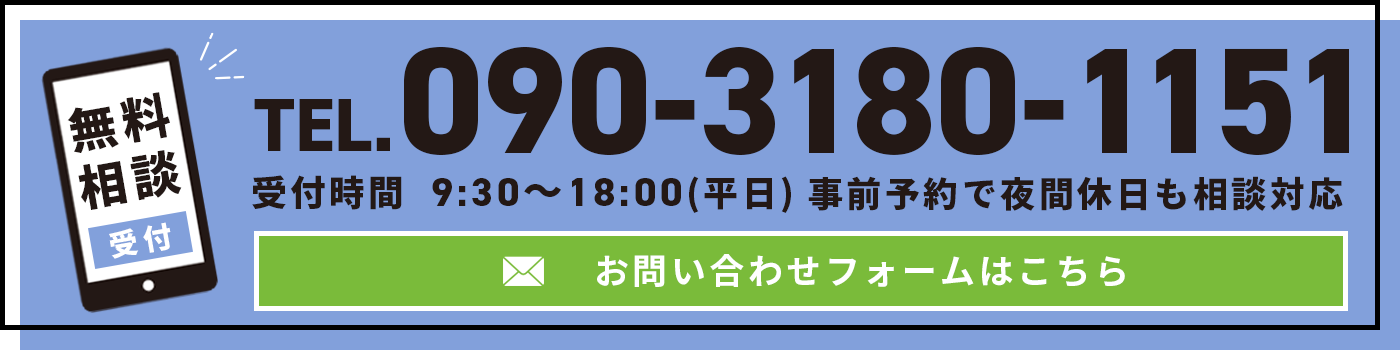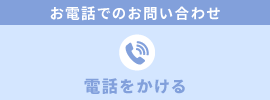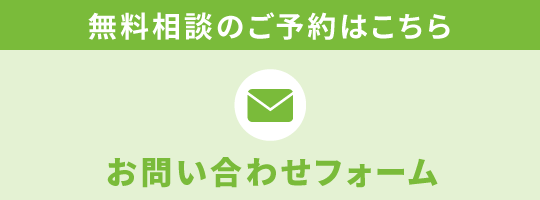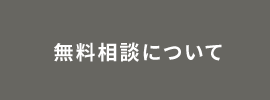このページの目次
1.はじめに
このページでは、古物商許可に関する基本的な内容や、許可の取得方法に関して解説していきます。
2.古物商許可とは
古物商許可は、「古物」を売買する際に必要となる許可です。
「古物」に該当するものは、古物営業法に規定があり、「一度使用された物品」「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義されています。
一般的に中古品をイメージしますが、新品の物でも一度消費者の手に渡ったものは古物に該当します。
これらの「古物」を営利目的で継続的に売買を行う場合、古物商許可が必要になります。
また、古物商許可を取得せずに取引した場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があるため、注意が必要です。
3.古物の具体例
古物は次の13品目に分けられており、古物商許可を取得する際は取引を行う品目を明示する必要があります。
| 品目 | 具体例 |
| 1.美術品類 | 書画、彫刻、工芸品、絵画、骨董品等 |
| 2.衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 3.時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 4.自動車 | 自動車やその部分品を含む。 |
| 5.自動二輪車・原付 | これらの部分品を含む。 |
| 6.自転車類 | その部分品を含む。 |
| 7.写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 8.事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 9.機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
| 10.道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
| 11.皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
| 12.書類 | 本、雑誌等 |
| 13.金券類 | 商品券、乗車券及び郵便切手等 |
4.古物商許可が必要なケース
古物商許可はお店を開いて事業として売買を行う場合だけでなく、個人が行う取引でも必要となる可能性があります。最近では、フリマアプリやオークションサイト、ネット店舗での販売等を行う個人の方が多くいらっしゃいますが、中古品を継続的に仕入れ、販売を行う場合には、古物商許可が必要になります。
具体例
・時計その他宝飾品の販売
・トレカ、玩具等の販売
・衣類等の販売 など
フリマアプリ等で販売する際に、必ず古物商許可が必要なわけではなく、あくまで営利目的で継続的に仕入れ、販売を行う場合に許可が必要となります。
そのため自身が着用し、着なくなった服を販売する際や、お子さんが使わなくなったおもちゃを販売する場合には、許可は不要となります。
(許可の必要性に関しては、自身で判断せず専門家に確認することをお勧めします。)
5.古物商許可取得までの流れ
次に古物商許可を取得する際の、準備から申請、取得までの流れを解説します。
申請する古物の品目によって、別途手続きが必要なケースもありますが、大きな流れは以下のようになっています。
許可取得までの流れ(個人の場合)
1.営業所の確保
↓
2.申請書類の作成・収集
↓
3.申請
↓
4.審査
↓
5.許可取得
1.営業所の確保
まず初めに、営業所の用意が必要です。
実店舗で営業を行う場合には、その店舗が営業所となりますが、ネット上で取引する場合でも、営業所が必要になります。
また営業所は実在している必要があり、バーチャルオフィス等の仮想空間上のものは、営業所として認められません。
しかし必ず店舗が必要となるわけではなく、自宅等を営業所として申請することも認められています。
その際注意が必要な点は、賃貸物件の場合です。
通常賃貸物件の場合、契約書の目的の欄は「住居用」となっています。
そのため営業所として使用する場合には、事前に管理会社等へ営業所として使用することの可否を確認する必要があります。
2.申請書類の作成・収集
申請には、各種申請書類と、住民票等の証明書類が必要になります。
申請書の様式は、申請先である管轄の警察署で入手できるほか、ホームページからダウンロードすることも可能です。
許可を受ける品目によって、追加の資料が必要となる場合もあるため、事前に申請先へ確認することをお勧めします。
3.申請
申請は営業所所在地を管轄する警察署の担当課に行います。
申請方法は窓口での受付のみとなっており、郵送や電子申請では申請できません。
また受付時間は各申請先によって違いがあるため、事前確認が必要です。
4.審査
審査期間はおよそ40日とされています。
書類の修正や追加資料を求められる場合もあり、対応が遅れると審査期間にも影響が出るため、連絡があった際には早急に対応する必要があります。
5.許可取得
申請内容に問題がない場合、許可取得となります。
6.申請費用
古物商許可の申請手数料は「19,000円」となっています。
このほかに、住民票、身分証明書の発行手数料や、申請手続きを行政書士に依頼する場合の、行政書士手数料が発生します。
7.欠格要件
古物商許可には以下のような欠格要件が定められており、申請時に該当する場合や、後から該当してしまった場合は、許可を受けられません。
欠格要件
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
・住居の定まらない者
・暴力団関係者
・未成年者 など
8.古物商許可業者の義務
古物商に盗品が持ち込まれるケースは大変多く、問題となっています。
そのため古物商許可業者には、次のような義務が設けられています。
法第15条「取引の相手方の身分確認」
古物商は古物を買い受ける場合や、交換する場合には、取引相手の真偽を確認する義務があります。
確認の方法は一般的に、運転免許証やマイナンバーカードの確認や、住所・氏名・年齢等を書面等に記載してもらう方法があります。
例外として、1万円未満の買取を行う際には不要とされていますが、次の物を買い取る際には、必ず本人確認が必要です。
※金額にかかわらず本人確認が必要な物
・自動二輪車
・原付
・テレビ
・ゲームソフト
・CD・DVD等
・書籍 など
また、自身が相手に売却したものを、当該相手から買い取る場合にも、本人確認は不要とされています。
法第15条「不正品発見時の警察への通報」
古物商は、盗品等の不正品を発見した際や、その疑いがある場合には、直ちに警察官に申告する必要があります。
これを行わずに流通させた場合、古物商自体が処罰の対象となるため、注意が必要です。
法第16条「取引記録の保存」
古物商は古物の売買を行った際、次の事項についてその都度、帳簿又は電磁的方法によって記録する必要があります。
後々事件等が発覚した際には、警察の求めに応じて提示する必要があります。
(記録事項)
・取引の年月日
・古物の品目及び数量
・古物の特徴
・取引相手の住所、氏名、職業及び年齢
・取引相手の真偽を確認するために取った措置の区分
9.最後に
フリマアプリやネット経由の売買の影響で、誰でも簡単に売り買いができるようになっていますが、古物商許可の必要性の有無は、まだそれほど広く周知されていない傾向にあります。
自身が行っている取引が、実際には古物商許可が必要なケースに該当する場合もあるため、古物の売買には注意が必要です。
10.申請にあたって
弊社は古物商許可の申請代行も承っております。
各種申請書類の作成や、証明資料の収集など、許可取得に必要な手続きを一括して承っております。
古物商許可に関するご相談や質問は、お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。
(対応可能エリア:東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県 ※一部エリアを除く)