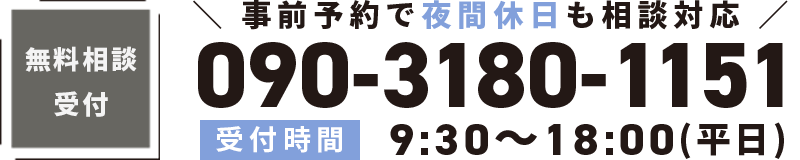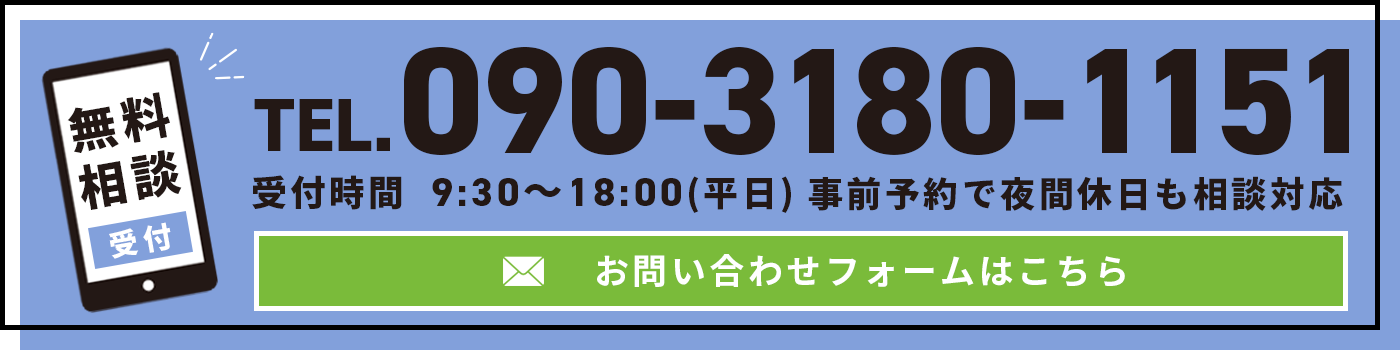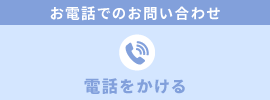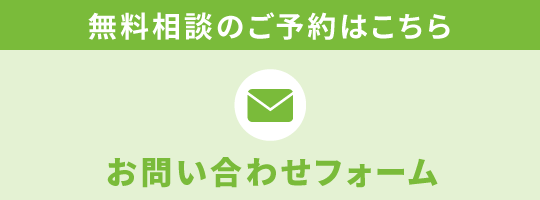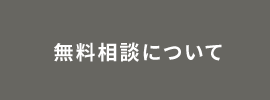このページでは、建設業許可申請に必要な書類と、その提出先について解説します。
申請書類は量が多いため、まずは全体像を把握したうえで、それぞれどういった書類なのか解説していきます。
このページの目次
必要書類一覧
- 建設業許可申請書(第1号様式)
- 役員等の一覧表(別紙1)
- 営業所一覧表(別紙2(1))
- 収入印紙等貼付用紙(別紙3)
- 専任技術者一覧表(別紙4)
- 工事経歴書(第2号様式)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(第3号様式)
- 使用人数(第4号様式)
- 誓約書(第6号様式)
- 経営業務の管理責任者証明書(第7号様式)
- 経営業務の管理責任者の略歴書(第7号様式別紙)
- 健康保険等の加入状況(第7号の3様式)
- 専任技術者証明書(第8号様式)
- 実務経験証明書(第9号様式)
- 指導監督的実務経験証明書(第10号様式)
- 令3条に規定する使用人の一覧表(第11号様式)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(第十12号様式)
- 令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(第13号様式)
- 株主(出資者)調書(第14号様式)
- 財務諸表一式
法人の場合
・貸借対照表(第15号様式)
・損益計算書・完成工事原価報告書(第16号様式)
・株主資本等変動計算書(第17号様式)
・注記表(第17号の2様式)
・附属明細表(第17号の3様式)
個人の場合
・貸借対照表(第18号様式)
・損益計算書(第19号様式) - 営業の沿革(第20号様式)
- 所属建設業団体(第20号の2様式)
- 主要取引金融機関名(第20号の3様式)
その他提出書類
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 納税証明書
記載内容
① 建設業許可申請書(第1号様式)
建設業許可申請書には、取得したい許可の業種、会社や代表者の情報を記載します。
記入方法は細かく指定がされており、記号や数字での記入も多いため、注意が必要です。
② 役員等の一覧表(別紙1)
役員等に該当する方をすべて記載します。
勤務形態が常勤か非常勤かの記載が求められているため、経営業務の管理責任者との整合を確認しましょう。
③ 営業所一覧表(別紙2(1))
建設業法上の営業所をすべて記入します。
営業所に該当するかどうかで、許可要件に関わってくるため、注意が必要です。
④ 収入印紙等貼付用紙(別紙3)
申請手数料の支払いの際に購入した、収入印紙等をこの書類に貼付けます。大臣許可、知事許可の違いにより手数料の額が異なる点や、行政庁によっては現金での支払いを求められることもあるため、事前に確認しましょう。
⑤ 専任技術者一覧表(別紙4)
営業所一覧表(別紙2(1))に記入した営業所ごとに、配置する専任技術者を記入します。
専任技術者の資格、実務経験と、取得予定の許可業種の技術者要件を確認しましょう。
⑥ 工事経歴書(第2号様式)
許可申請者がこれまで受注してきた工事を記入します。
公共工事を受注する場合、記入方法が変わってきます。また、記入方法も複雑で、細かいルールがあるため、作成には注意が必要です。
⑦ 直前3年の各事業年度における工事施工金額(第3号様式)
許可申請者が申請の直前3年間の各事業年度に完成した、建設工事の請負代金の額を記入します。 記入欄は「元請」「下請」の違いや、「公共工事」か「民間工事」の違いによって分けて記入する必要があります。また、⑥工事経歴書(第2号様式)との整合が必要な点もあるため、合わせて確認しましょう。
⑧ 使用人数(第4号様式)
各営業所の従業員の数を記入します。
「使用人」の数には、役員や個人事業主も含まれます。
⑨ 誓約書(第6号様式)
欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。
虚偽の申請には罰則が設けられているため、欠格要件をしっかり確認したうえで記入しましょう。
⑩ 経営業務の管理責任者証明書(第7号様式)
この書類は申請業者に経営業務管理責任者を配置していることと、その方が経営業務管理責任者としての要件を満たしていること証明する書類です。
前職の経験を利用して要件を満たす場合、前職の会社から押印をもらう必要があるため、準備に時間がかかる書類の1つです。
⑪ 経営業務の管理責任者の略歴書(第7号様式別紙)
⑩に記載の方の職歴を記入します。
経営業務管理責任者としての経験を確認するため、役職が変わったタイミングも、細かく分けて記入します。
⑫ 健康保険等の加入状況(第7号の3様式)
建設業許可要件の、社会保険の加入状況を確認する書類です。
営業所ごとに社会保険の種類、加入の有無を記入します。
⑬ 専任技術者証明書(第8号様式)
この書類は、各営業所に専任技術者を配置していることと、その方が専任技術者としての要件を満たしていることを証明する書類です。
資格区分等の記入には別表の数字を用いるため、わかりにくい部分もあります。そのため1つ1つ確認したうえで、慎重に進める必要があります。
⑭ 実務経験証明書(第9号様式)
専任技術者要件を実務経験によって満たす場合に必要な書類です。そのため、資格で証明する場合には提出不要となります。
実務経験年数の加算方法は許可行政庁によって若干異なるため、注意が必要です。
⑮ 指導監督的実務経験証明書(第10号様式)
特定建設業許可の申請を行う場合に必要な書類です。
一般建設業許可の場合には提出不要となります。
⑯ 令3条に規定する使用人の一覧表(第11号様式)
支店営業所を設ける場合に、配置が必要な令3条使用人を記入する書類です。
支店がない場合は提出不要となります。
⑰ 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(第十12号様式)
申請者が個人の場合は申請者本人、法人の場合は②で記入した役員について、1人1枚ずつ記入します。
⑱ 令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(第13号様式)
⑯に記入した令3条使用人に関して、1人1枚ずつ記入します。
⑲ 株主(出資者)調書(第14号様式)
許可申請者が法人の場合に必要な書類です。
株式会社の場合、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、その他の法人の場合、出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている方について記入します。
⑳ 財務諸表一式
法人、個人の違いによって必要な書類が異なります。
注意すべき点は、それぞれ建設業許可申請専用の様式であるという点です。
決算や税務申告にあたって作成したものを、そのまま提出することはできず、それぞれ指定の様式を使用し、別途作成する必要があります。
法人の場合
- 貸借対照表(第15号様式)
- 損益計算書・完成工事原価報告書(第16号様式)
- 株主資本等変動計算書(第17号様式)
- 注記表(第17号の2様式)
- 附属明細表(第17号の3様式)
個人の場合
- 貸借対照表(第18号様式)
- 損益計算書(第19号様式)
㉑ 営業の沿革(第20号様式)
許可申請業者の創業から現在に至るまでの沿革を記入します。
㉒ 所属建設業団体(第20号の2様式)
加入している建設業団体がある場合に、その名称と加入日を記入します。
未加入の場合でも「なし」と記入の上、提出が必要です。
㉓ 主要取引金融機関名(第20号の3様式)
主に取引を行っている金融機関を、すべて記入します。
その他提出書類
登記されていないことの証明書
欠格要件の確認資料として提出が求められています。
この書類によって、成年後見制度の利用登録の有無がわかり、登録されていると欠格要件に該当してしまいます。
身分証明書
この書類の確認事項として、① 禁治産又は準禁治産の先刻の通知を受けていないこと、② 成年被後見人や被保佐人に該当しないこと、③ 破産宣告又は破産開始の決定の通知を受けていないことを証明します。
納税証明書
「納付すべき額及び納付済みの額」を確認します。
新設法人の場合、営業実績がないため、提出は不要です。
確認書類
上記の申請書とは別に、申請書の内容を確認する書類が必要になります。それぞれ該当する要件により、求められる書類が変わるため、注意が必要です。
経営業務管理責任者に関する書類
- 住民票等の現住所が確認できる書類
- 健康保険証の写し
- 確定申告書
- 商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書、閉鎖謄本等
専任技術者に関する書類
- 住民票等の現住所が確認できる書類
- 健康保険証の写し
- 資格証の写し
- 指定学科の卒業証書
- 工事契約書、請負契約書、注文書等
申請書類の提出先
申請書類の提出先は、大臣許可、知事許可の違いによって変わってきます。
大臣許可 → 地方整備局
知事許可 → 都道府県知事
それぞれ担当課に、持参又は郵送にて提出します。
最後に
このように建設業許可申請には大変多くの書類の準備、作成が必要になります。そのため許可申請に関する手続きを、専門家に依頼する方も多くいます。
弊社は建設業許可専門の行政書士法人です。書類作成に不安がある方、どういった書類が必要なのか確認したい方など、許可申請に関するお悩みは、ぜひ一度ご相談ください。