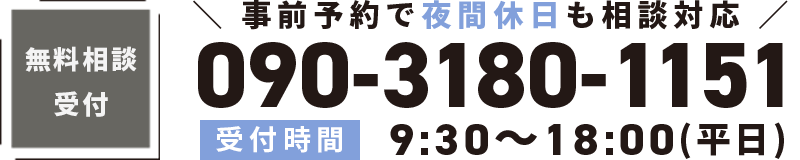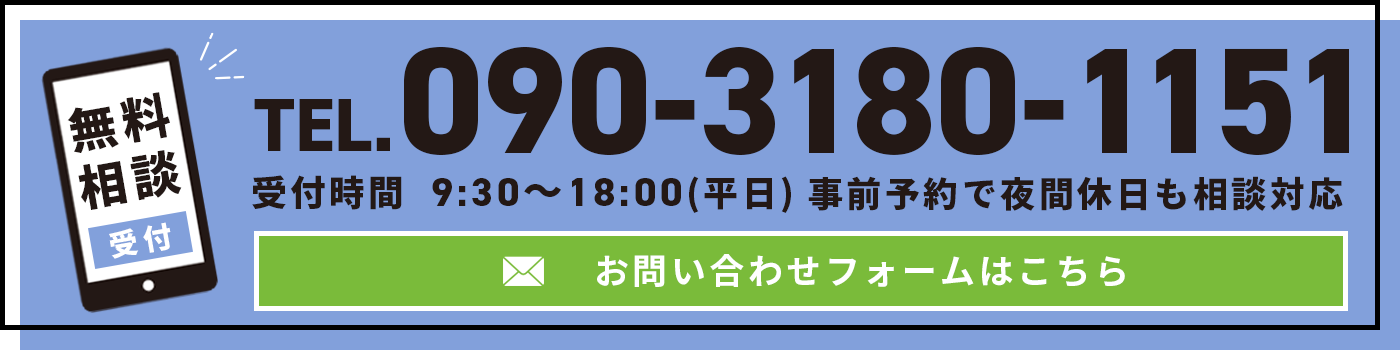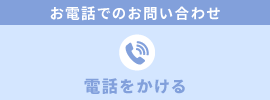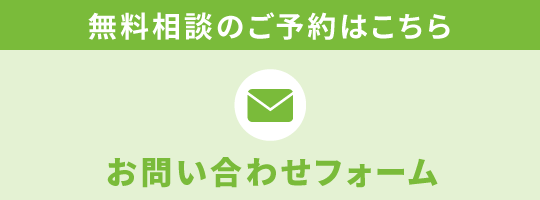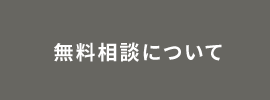このページの目次
1.公共工事の入札参加資格とは
建設業を営む事業者様の中には、国や地方自治体が発注する「公共工事」を受注したいと考える事業者様も多くいます。
しかし公共工事は誰でも受注できるものではなく、決められた手続きを行ったうえで「入札参加資格」を得た建設業者だけが、落札できる仕組みとなっています。
この記事では、公共工事の入札参加に関する概要や、手続きの流れを解説していきます。
2.公共工事について
2-1.公共工事とは
「公共工事」とは、国や地方自治体などの行政が発注者となって行う工事です。道路や河川、上下水道などのインフラ整備や、学校や病院などの公共施設の建設・改修工事が該当します。
2-2.公共工事の特徴
| 発注者 | 国、地方自治体、公的機関(国土交通省、防衛省、市役所など) |
| 受注者 | 建設業許可を持つ建設業者(要件を満たした業者のみ) |
| 目的 | 国民生活の安全・快適性の確保、地域の発展、災害対策など |
| 財源 | 税金(一般財源、補助金、交付金など) |
2-3.主な公共工事の例
・道路工事(高速道路、国道、市道などの整備や修繕)
・河川工事(堤防の整備等)
・上下水道工事
・学校・病院・庁舎などの公共施設の建設や改修
・橋梁・トンネルの建設や補修
・港湾・空港整備
・防災関連工事(土砂災害防止、地震対策など)
ここで重要なのは、受注者は要件を満たした建設業許可業者のみである点と、財源が税金であるということです。
税金を使って行う以上、無駄な費用や欠陥があってはいけません。そのため事前に入札に参加する業者を審査することで、適した業者のみが工事を行うような制度となっています。
3.公共工事入札参加の条件
公共工事の入札参加資格を取得するためには、以下のような条件があり、すべてクリアする必要があります。
〇建設業許可を取得していること
公共工事の入札参加資格を取得するためには、建設業許可を取得していることは必須条件になります。
公共工事ではない軽微な工事のみを受注する場合には、建設業許可は不要とされていますが、公共工事の入札参加資格を取得するためには、金額にかかわらず必ず建設業許可を取得している必要があります。
建設業許可の取得には、許可要件の適合、書類準備、申請というようにかなりの時間がかかるため、入札参加資格を取得するまでのスケジュールに注意が必要です。
〇経営事項審査を受ける
経営事項審査は公共工事を受注しようとする建設業者に対して、経営状況や技術力などを数値(点数)で評価する制度です。
以下の項目ごとに点数がつけられ、総合評定値(P点)を算出します。
| 項目 | 内容 |
| 経営状況分析(Y点) | 財務の健全性(負債、収益性、財務状況等) |
| 経営規模(X1、X2点) | 完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益の額など |
| 技術力(Z点) | 技術者数、元請金額など |
| 社会性(W点) | 労働福祉状況、建設機械保有数(社会保険加入など) |
| 総合評定値(P点) | 上記すべてを加味した総合点 |
※総合評定値(P点)算定式
0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W) = 総合評定値(P点)
このP点をもとに、入札参加資格の格付けが行われます。
経営事項審査は受けるだけでなく、どれだけP点をあげられるかが重要になります。裏技はではありませんが、中には入力方法の違いで点数が大きく変わる可能性もあるため、行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。
〇その他の条件
・税金の滞納がないこと
・反社会的勢力等に該当しないこと など
反社会的勢力等に該当しないことに関しては、建設業許可の要件にもなっているため、通常問題ないかと思います。
税金に関しては、公共工事が税金によって行われる特性上、そもそも支払っていない業者に発注するのは不合理です。
そのため前提条件として各種税金の支払いは、滞りなく行っている必要があります。
4.公共工事の入札参加資格取得の流れ
ここからは入札参加資格取得までの流れを解説していきます。
手続きの大きな流れは以下のような順になっています。
①建設業許可の取得
②経営状況分析の申請
③経営事項審査の受信
④入札参加資格の取得申請
それぞれ解説していきます。
①建設業許可の取得
まずはじめは建設業許可を取得します。
条件の項目でも説明したように、建設業許可がないとそもそも入札参加資格を取得できません。
建設業許可取得について、詳しくは 建設業許可の申請について をご確認ください。
②経営状況分析の申請
経営状況分析は、経営事項審査を受信する前に、事前に行う手続きです。経営事項審査では総合評定値(P点)を算出しますが、そのP点を出すのに、経営状況分析(Y点)が必要になります。
経営状況分析の申請は、行政庁ではなく登録経営状況分析機関に申請を行います。
申請先の機関によって審査期間が変わるため、注意が必要です。
③経営事項審査の受信
経営事項審査は建設業許可の許可行政庁に申請を行います。
審査によって総合評定値P点を算出しますが、このP点には有効期間があり、審査基準日から1年7カ月とされています。
詳細は各ページで解説しますが、審査完了日ではなく、審査基準日から1年7カ月のため、入札参加手続きを行うと、1年弱しか期間が残りません。そのため継続して入札参加資格を取得するためには、毎年経営事項審査を受審する必要があります。
④入札参加資格の取得申請
経営事項審査受審後、入札参加資格を取得するためには、自治体ごとにそれぞれ申請を行う必要があります。申請の受付期間や資格の有効期間は、自治体ごとに異なるため注意が必要です。
ここまで完了して、ようやく公共工事の入札が行えるようになります。
5.まとめ
上記のように公共工事を受注するためには、多くの手続きを正確に行う必要があり、はじめての方にとってはかなりの労力と時間が必要になります。そのため申請にあたっては、一度専門家へご相談することをお勧めします。
弊社は経営事項審査、入札参加資格代行申請を行っております。
・何から準備したらいいのか分からない
・経営事項審査で何点くらいになるのか知りたい
・いつごろから入札に感化できるのか など
経営事項審査、入札参加に関するご相談はお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にて、ご連絡ください。